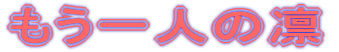 3章
3章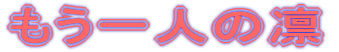 3章
3章
そして決戦の朝。
目覚めると、隣には遠坂の寝息が聞こえる。
俺はしばし遠坂の寝顔を観賞した後、起こさぬように注意しながらベッドから這い出た。
これから戦いに向かう事になる。
ならば万全の用意をしなければならない。
と言いつつも、用意するものなど俺にはないのだが。
せめて遠坂のために美味しい料理を作ってあげるだけだ。
そう思った俺は一足速く、朝飯を作り始めた。
俺がフライパンを振リ終わると、珍しく遠坂が早起きしてきた。
「おはよう、早いのね、士郎」
なんと! 今日の遠坂は寝ぼけていなかった、珍しい事もあるもんだ。
「む、なによ。鳩が豆鉄砲喰らった様な顔をして。
そんなに、わたしが早起きしたのが珍しいのっ?」
「いや、遠坂が寝ぼけてない朝って初めてだから、驚いただけだ」
「ふんっだ。昨日は良く眠れたから、寝起きがいいだけよ」
さらさらの髪をかきあげ、そんな事を言う遠坂は少しだけ照れていた。
「そうか、それは良かった。
―――なら朝飯を食べたら今日の計画を練ろう。遠坂には作戦があるんだろう?」
「あったりまえでしょう。
今日この日を十年間待ちわびてたんだから。作戦なんて腐るほどあるわ」
臓硯が復活するまでの十年間、遠坂はこの日をずっと待っていたんだろう。
全てを失った日から、今日まで鍛え続けた剣と魔力。
全てぶつけてヤツを倒すつもりだ。
「そうか、それならとりあえず朝飯にしよう。腹が減っては戦が出来ぬ、ってな」
「それもそうね、じゃあ早速頂きましょう」
俺たちの立てた作戦はこうだった。
臓硯は間違いなく間桐の屋敷にいる。
あの地がヤツにとっての最良の結界だからだ。
そして俺たちが近づけば、多分あの影が大量に出てくるだろう。
十匹や二十匹では済まないかもしれない。
それだけの数の使い魔を掻い潜って、臓硯の元に辿り着くのは不可能に近い。
だから臓硯以外の敵は、全て俺が相手をする。
遠坂にはこの日のための切り札があるらしい。
臓硯と一対一になれば、確実に勝利できると言い切った。
なら俺は、遠坂の為に最高の舞台を作るだけだ。
「質問は?」
「特にない、それで決行は?」
「今すぐよ、ヤツは夜になればなるほど魔力が増大する。
早ければ早いほどわたし達に有利よ」
「分かった、ならば行こう。
―――俺はお前の剣となり、盾となる事を誓う。
必ず生きて帰るぞ、二人で」
「当然でしょう。
士郎、わたしを残して、ひとりで死んだら許さないから」
俺たちは、今この瞬間から、お互いの背を守り守られるパートナーだ。
俺の命は遠坂と共にあり、遠坂の命は俺と共にある。
最後に一回だけ軽いキスをして、俺たちは遠坂邸を出発した。
遠坂邸から下ってすぐの所に間桐の屋敷はある。
俺の記憶と寸分違わぬその屋敷は、唯一つだけ大きく異なる点があった。
「すごい妖気ね……」
その洋館を取り囲む結界は、遠坂の屋敷にも勝るとも劣らない。
そしてこの魔力が、五世紀もの時を生きてきた大魔術師の実力に他ならない。
絡みつく空気は、まるで虫のように体に吸い付く。
ただ歩いているだけで魔力を消耗していくような、強力な負の結界。
「このくらいは覚悟していたわ。士郎、怖気づいてないでしょうね?」
「当たり前だ、俺は俺のすべき事をやるだけさ。必ず遠坂を臓硯の元に送り届けてやる」
「ありがとう、この戦いが終わったら……」
「終わったら?」
「……ううん、何でもない。今は余計な事を考えてる余裕はないんだったわね」
頬をピシャッと叩き、遠坂は気合を入れ直した。
そうして結界内に足を踏み入れたすぐ側で、ヤツは俺たちを待っていた。
「ほほう、わざわざ殺されに来るとは、気でも違ったか? 遠坂の娘よ」
目の前にいるのはただの古ぼけた爺さんにしか見えなかった。
魔力の猛りも感じない、しかしそれだけではない筈、何か切り札を隠し持っているに違いないのだ。
そうでなければわざわざ俺たちの前に現れる筈もない。
その辺は遠坂も分かっているようだ。
不用意に飛び掛りはせず、様子を伺っている。
俺たちは顔を見合わせ、周囲に注意を払う。
「ん? なにやら助っ人でも連れて来たのかの? 死に急ぐとは若いくせに愚かな奴じゃ」
老人は詰まらなそうに言い捨てて、俺の顔を侮蔑の表情で覗き見る。
「なっ! 貴様は衛宮士郎、な、何故ッ貴様がここにいる!? しかもその姿は何だ!?」
臓硯は俺の姿を確認すると急に慌てだした。
しかも今のセリフ……
臓硯は確かに『エミヤシロウ』と言った。
コイツは俺の事を知っているのだ。
この世界で俺の事を知っていた最初の人物が、最悪の魔術師だったなんて悪い冗談みたいだ。
遠坂は、何も言わずに、目の前の老魔術師を睨みつけている。
「聞いてない! 聞いてないぞっ、貴様がいるなんてっ」
何故だか知らないが動揺しているなら、付け入るチャンスだ。
「―――遠坂」
俺は遠坂に目配せをする。
そしてそれに応じて遠坂が飛び掛ろうとする直前。
「二度の不覚は取らぬっ! もはや手加減は無用じゃ、出でよ、我が使い魔よ!!」
ヤツがそう唱えた瞬間、周囲に魔力の余波が広がる。
臓硯はピョンと後方に跳び、間合いを取る。
「来るぞ!」
あと数瞬の後、あの影達が大量発生すると思った。
だが、現れた魔は俺たちの予想を遥かに上回る質量を持っていたのだ。
庭の中心に出来た魔力の揺らぎ、そこから現れたのは影なんかじゃなかったのだから。
身の丈は優に二メートルを超え、頭が猿、胴が狸、手足が虎、尾は蛇で出来ていた。
溢れる魔力は強大、轟く気迫は裂帛。
昨日読んだ「平家物語」で語られていた古代日本の魔獣。
「鵺!!」
ゴァーーーーーーーーッ
ビリビリと大気が震えるほどの咆哮をあげる大妖獣の姿がそこにあった。
「なんで、なんで!? 鵺は父さんが確かに殺した筈っ、わたし、この目でしっかりと見たもの!」
鵺の登場で余裕を取り戻したのか、臓硯は見るからに喜々としている。
「甘いぞぃ、甘いのだ、遠坂の娘よ。鵺は死んでも蘇るという伝説を知らぬのか!?
鵺はマスターが無事ならば何度でも蘇る化け物なのじゃよっ」
「くっ!」
「貴様らでは鵺には勝てん、それは十年前の勝負でわかっているじゃろう」
ふぉふぉふぉ、と笑う臓硯。
それに対し、唇をかみ締める遠坂。
「大人しく食い殺されてしまえ―――では、わしは失礼するぞ」
臓硯は消えるように屋敷の中へ帰っていった。
それを黙って見送るしか出来ない俺たち。
この場で隙を見せれば、即座にぬえに食い殺される。
それほどの妖気を目の前の化け物は放っていた。
俺たちは目線を鵺から外すことなく、作戦を練る。
どうやら鵺は俺たちを積極的に追いかけてくる気はないらしい。
大方、玄関の守りを優先しろとでも命令されているのだろう。
「ごめんね、士郎。これはわたしのミス。鵺が生き返るなんて気づかなかった」
「今はそんな事を言ってる場合じゃない、この場でヤツを倒すんだろ?」
「む、無理よ。何とか二人で隙を見て逃げ出しましょう!」
「それは出来ない。このチャンスは千載一遇だ。逃すわけにはいかない」
「それは何故?」
「これほどの魔力を持つ魔獣だ、召喚している臓硯の負担は相当なもの。
ここでコイツを引き止めるコトができれば、臓硯を倒すのは容易い筈だ」
「引き止める!? まさか士郎、アナタ……」
「そのまさかだ、遠坂。
―――俺が一人であの化け物の相手をする。お前は屋敷の臓硯を追うんだ」
「無茶よ、そんなの!?」
「無茶でもやる。
遠坂、仇を討つんじゃなかったのか? 10年間ずっと考えてきたんだろ?
だったらお前はそのことだけを考えるんだ」
「でも!?」
「遠坂!
俺の事を信じられないのか? 俺はそんなに頼りにならないのか?」
「…………!」
「俺を信じて、先に進めっ。
―――必ず生きて俺も後を追うから」
そこで新たな作戦は決まった。
俺たちは返事をする代わりに一瞬だけ手を握り合い、そして横に弾け跳んだ。
左に遠坂、右に俺。
瞬時に鵺の左右に別れる。
俺の役目は、敵の意識をこちらに向かせること。
それには威力が必要だった。
目の前の魔獣を吹き飛ばすほどの強力な攻撃が―――
俺は斜め上に飛び上がり、空中で即座に弓と矢を投影する。
愛用の弓に番える矢は、4本の偽・螺旋剣。
最大の破壊力、壊れた幻想で一気に勝負を賭ける。
跳躍の頂点から俺は四束中を一息に射放つ。
狙うは眼下に潜む東洋の魔獣。
俺に狙われているのに、ぴくりともしないその姿が逆に不気味だった。
「これに耐えられるかーーっ!」
襲い掛かる不安を振り払うように、俺は必殺の矢を降り注いだ。
朝焼けに映える流星群。
一つ一つが最大級の破壊力を持つ、壊れた幻想。
正に流れ星となって標的を貫いた。
庭が抉れ、爆音が響き渡る。
四連、全弾間違いなく命中した―――。
ならば足止めなどとは言うまい。
これで生きていられる方がおかしいのだから。
無論、遠坂は今の攻撃の隙に屋敷に潜入している。
鵺を倒したらすぐにでも後を追わねば。
だが、やはりというか、予想通りというか、この程度で死んでくれる生易しい敵ではなかった。
いや、今の攻撃はこの程度と言っていいレベルじゃない。
今の攻撃に耐えられる魔獣など存在しないのだ。
つまりこの1000年もの間存在し続けている妖獣は、既に幻獣レベルの力を持つという事だ。
徐々に煙が消えて、目の前には抉れたクレーターが四つ現れる。
そしてその中心で、何事もなかったように座り続ける幻獣鵺。
「ガーーーーーーッ」
咆哮を上げ、敵とみなした俺を威圧する。
―――来るッ
幻獣レベルの敵に、俺の力でどこまで戦えるのか。
弱気になる心に喝をいれ、二対の剣を構えたのだった。
「ハァハァ、ハァ……もう、何でこんなに広いのよ、この屋敷っ」
何枚のドアを蹴破っただろうか。
一向に見つからない臓硯に、わたしの心は千路に乱れた。
―――急がないと
外では士郎が戦っている。
いくら士郎でもヤツには勝てない。
だから急がないと。
わたしが急いで臓硯を倒せば、士郎も助かる。
「ハァハァ……くそっ」
その時、屋敷全体が震えるほどの咆哮が響いた。
「ガーーーーーーッ」
鵺の咆哮だ。
―――やばい、戦闘が始まってるっ
ここに来て私の焦りは頂点を向かえ、そして限界を超えてしまったようだ。
過ぎたる焦りは冷静さを呼び起こし、わたしは冷静に屋敷の解析を始めた。
今まで通った部屋、蹴破った扉、それらの情報から屋敷の構造を導き出す。
そうして気づいた。
―――臓硯の魔力は屋敷にはない
ならばきっと地下室があるはず!
そしてわたしの推理通り、屋敷の西南の方角に下り階段を発見し、わたしは一も二もなく駆け下りていた。
そこは異様な空間だった。
満ち溢れる臭気と陰気、そしてギチギチと響く蟲の音。
―――間違いない、ここに臓硯がいる。
確信したわたしは、そのままの勢いで慎重に階段を下りて行った。
そうして降りた先に、少し広めの部屋があった。
その中心に鎮座する怨敵。
「臓硯!」
「おや? 衛宮の小僧を生贄にしてここまで来たか。随分と酷いことをするものじゃな」
ふぉふぉふぉと笑う声が、わたしの怒りを増長させる。
しかし、冷静さを欠いて勝てる相手じゃない。
わたしは全ての精神をコントロールに当て、冷静さを保ち続けた。
「あら、随分余裕なのね。ここまで入り込まれてるのよ、もっと慌てて欲しいものね」
「慌てる必要がどこにあるのじゃ?」
「くっ、目の前にわたしという敵がいるのが見えないのかしら!」
「見えんな、敵など。
わしの前には小娘が一人いるだけじゃ、さて、どのように料理してくれようか……」
「……! きっさまーっ!」
もう冷静さなど保っていられない。
わたしは右手に持つ細剣に魔力を通し、目の前の老魔術師に斬りかかる。
しかし、その直前に、わたしの魔術師としての直感が警告を発していた。
すんでのところで踏みとどまり、そこで気づいた。
わたしを取り囲む、数万、数十万の蟲の目の光に―――
鵺の素早い攻撃に、俺は防戦一方となった。
いや、ただ素早いだけならどうとでもなる。
人と違い、予備動作のない獣の動きが、俺には読めなかったのだ。
実際の数倍のスピードに感じるその攻撃を、俺は右に左に避け続けていた。
しかし、目の前の幻獣に全く隙がないわけでもなかった。
―――隙はある、あるんだっ
そう、敵は防御に関しては素人だった。
幾度となく、両手に構える干将・莫耶でその隙を切りつける。
しかし、既に二対の剣は刃こぼれでボロボロだった。
当然、鵺の体には傷一つない。
そう、この最高の防御力こそが、鵺の最大の武器なのだ。
一体遠坂の親父さんは、コイツをどうやって倒したのだろう。
しかし今俺が考えねばならないのは、コイツを妥当する方法だ。
―――考えろ、考えろ!
鵺の鋭い爪を紙一重でかわしながら、俺の脳はフル回転を続けていた。
弓が弱点だと思っていた。
源頼政は、弓で鵺を射殺したと伝承にある。
しかし弓は通じなかった。
それなら違う弱点があるはずだ。
俺の意識は遠坂の部屋で読んだ「平家物語」の一ページに跳んでいた。
頼政は『蟇目の秘術』と呼ばれる陰陽道に精通していた、と書かれている。
そして「南無八幡大菩薩」と言葉を発し、鵺を射殺したのだ。
ならばその言葉こそ、鵺を倒すべき言霊に違いない。
実物を見たわけではなかった。
ただ挿絵を見ただけ、しかし、それでも十分に頼政の念が伝わったのは、あの本自体の魔力だろうか?
こうして目を閉じれば、あの弓が浮かんでくる。
創造理念、基本骨子、構成材質、製作技術、成長経験、蓄積年月、その全てがまるで実物のように紙から浮かんでくるのだ。
そう、まるで鵺を倒すのは俺の役目と言わんばかりに、俺の左手には『弓張り月』と呼ばれた、鵺殺しの弓が握られていた。
「グワァーーーーーーーーーッ!」
天敵ともいえる弓の登場に、鵺の絶叫が響き渡る。
なぜ? どうして? 心を乱す鵺の心境が、手に取るように分かる。
このチャンスを逃すわけにはいかないっ
俺は弓の弦を引き絞り、そして鳴らした。
鳴弦・弦象―――
弓の弦には古来より魔を払う役目がある。
三度打ち鳴らした鵺殺しの弓に、幻獣の動きは明らかに鈍った。
まるで手足に数百キロの重石を乗せているかのように、鵺の体を束縛する。
そして俺は矢を番える。
作り出した矢は無銘の剣。ここで宝具を使う必要はない。
肝心なのはこの後だ。
俺は弓に矢を番え、そして唱えた。
―――南無八幡大菩薩
その瞬間、矢は白い破魔の力に包まれ、薄く発光を始めた。
やはり、「南無八幡大菩薩」とは言霊だった。
言霊とはつまりは言葉に篭る力。
発する言葉に効果を持たせる、一種の呪いなのだ。
そして源頼政が作った言霊、それが鵺殺しの呪いだった。
「ガッ、グワァッーーーーーー!」
動かぬ体に鵺の絶叫は続く。
自らの死期を感じ、必死に逃げようとしているのだ。
しかし、お前をここで逃がすわけにはいかない。
俺は最大限に高まった破魔の矢を、目前の幻獣に向けて射放った。
白いオーラに包まれたその矢は、まるで紙を貫くかのように鵺の体を貫いた。
あれほどの強度を誇った鵺の体も、今はただの布切れだった。
「グゥワーーーーーーーーーッ!」
最後の絶叫が木霊する。
そして町全体に響くほどの音をたてて、鵺はその場に崩れ去った。
―――ここに勝負は決した。
巨獣の絶命を確認したのか、手に持つ弓も露と消え去った。
この宝具は鵺を倒す為だけに存在する弓だったのだ。
消え逝く弓に「ありがとう」とひと声かけ、俺は遠坂を追って屋敷に入った。
「随分とたくさんの蟲を集めたものね」
ふぉふぉふぉと、余裕を崩さぬ臓硯の様子を見る。
「そうでもない、これでもかなり減ってしまったのじゃよ」
「そう、これだけの数の蟲に囲まれて余裕ってワケね、
ふんっ、気に入らないわね、魔術師なら自分の魔術で勝負しなさいっ。
蟲の力だけで戦って、アナタには誇りというものはないの?」
「無いな、そんなもの。
挑発には乗らんぞ、わしが一声かければ、これら数万の蟲達が一斉に貴様に襲い掛かる。
貴様の命はわしの手の中と言うわけじゃ」
「そう、それならやってみたら? 時間稼ぎなんかしちゃって、本当は士郎がくるのが怖いんじゃないの?」
「きっ、貴様、遠坂の分際でわしを愚弄する気かっ。
―――そんなに言うなら殺してやろう、だが楽には殺さんぞっ、内臓から食いちぎって悶えさせてくれる!」
―――来るっ
そう感じたわたしは、右のポケットに潜ませてある魔具に魔力を通す。
「死ねい、小童めっ」
臓硯の合図とともに、全ての蟲が一斉にわたしに群がってくる。
もちろん防ぐ術は無い……普段のわたしなら。
わたしはポケットから取り出した魔具を展開し、球状に結界を張った。
結界に張り付いて、ギチギチと牙を鳴らす数万の蟲たち。
「なにっ、それは!?」
虫除けの加護―――
協会から取り寄せた一級品の魔術秘蹟。
「十年間、アナタを殺す事だけを考えてきたんだから、このくらいの用意はしてあるわ」
この結界が働いている間は、蟲たちはわたしに近づく事は出来ない。
「し、しかし、そんな結界が何分も持つものかっ。一分もすればわしの蟲たちが食いちぎるわっ」
だから一分あれば十分なのよ。
わたしはとっておきの切り札をここで使う。
十年前に一度だけ見せてもらった本当の奇跡。
今、臓硯を倒す為に借り受ける。
右手を中空に掲げ、左手で印を組む。
魔力量は十分、今のわたしならきっと使いこなせる!
そして自らを律する呪文を唱えはじめる。
―――I am the bone of my sowrd.
思い浮かぶのはわたしを守って死んだあの人。
―――Steelismybody,and fireismyblood
わたしに残してくれた、たった一つのこの魔術。
―――I have created over athousand blades.
Unaware of loss.
Nor aware of gain
辛かった―――この十年間、本当に辛い事ばかりだった。
それでも今日のために生きてきたの。
―――Withstood pain to create weapons.
waiting for one's arrival
だから失敗は許されない。
溢れる魔力がわたしの魔術回路を破壊し続けたとしても。
I have no regrets.This is the only path
暴走する魔力によって、折れてしまいそうな心に喝を入れる。
―――負けない。わたしは負けたりなんかしない。
―――Mywholelifewas "unlimited blade works"
最後の真名を告げるその瞬間、わたしは愛しいあの人を思い浮かべる。
―――士郎
かくして失われたはずの禁呪は完成する。
炎ともに作られたこの世界はわたしとあの人の心の中。
―――unlimited blade worksがそこには在った。
作り変えられた世界、無限の剣製。
その中心に立つわたしと蟲の魔術師。
もちろん蟲も全部連れて来た。これから始末しなければならないのだから。
「な、なんと! これは固有結界かっ!?
ま、まさか、貴様がこれほどの魔術を修めていようとは……」
臓硯の表情には焦りの色が丸見えだった。
「そう、あの人がわたしの為に残してくれた大魔術。
そしてアナタを倒す為に残してくれた希望」
わたしの作ったこの世界に、大した剣は存在しない。
見ただけで剣を複製し、貯蔵する。それが無限の剣製。
しかし、わたしには聖剣も魔剣も見る機会はなかった。
だからここにある剣はどれも二流の剣たちばかり―――たった一本を除いては。
そう、たった一本だけ、臓硯を倒す為にイギリスまで見に行った聖剣がある。
思い浮かべた瞬間、わたしの右手にその剣が顕現する。
手の中で光るその剣の真名は……
―――ワームスレイヤー
蟲殺しの聖剣。
この剣でなければ、臓硯を完全に殺しつくすことは出来ない。
右手に持つ剣に魔力を通す。
それだけで聖剣は光を発した。
その光はわたしの固有結界を等しく包み、次の瞬間には幾万の蟲たちは消滅していた。
「さすが、蟲殺しの聖剣ね。魔力を通すだけで全滅させちゃったわ」
その光に毒されたのか、わたしの世界「unlimited blade works」が崩れ始めていく。
しかし、もう固有結界は必要ない。
わたしの右手には臓硯の天敵とも言える聖剣が握られているのだから。
崩れ落ちる固有結界を待ち、目前で震える臓硯を睨みつける。
「確実に殺すわ。もう二度と復活なんて出来ないように……」
その言葉とともに、炎の空と剣の墓場は何事もなかったように陰湿な地下室へと置き換わっていた。
「遠坂っ」
カンカンカンと地下室の階段を駆け下りる。
まだ遠坂の魔力を感じる事が出来る。
生きてる、遠坂は生きてるんだ。
なら急がないと、アイツは最後の最後で大ポカをしでかすヤツだ。
俺がフォローしてあげないと……
「遠坂っ」
飛び降りた地下室の広場には、薄く光る剣を持つ遠坂と、腰を抜かしてその場にへたり込む臓硯がいた。
どうやら大勢は決しているようだった。
俺は安堵の表情を浮かべ、遠坂に近寄ろうとする。
「士郎。まだ勝負はついてないわ、気を抜いちゃダメよ」
遠坂は、俺に振り向きすらせず冷たく言い放った。
その姿は正に冷徹な魔術師。
視線は決して敵から外さず、これから眉一つ動かさずにトドメをさすのだろう。
「ひぃぃぃぃ、なんで貴様がその剣をぉぉ、その剣をぉぉお」
恐怖で冷静な思考能力を失っているのか、臓硯は剣の事ばかりを気にしている。
剣?
その剣は一目見て分かった。
聖剣、それもかなりのレベルの聖剣だ。
しかし、驚くのはそこじゃなかった。
―――蟲殺しの聖剣
そうか、そういう手があったのか。
なぜ遠坂がそんな貴重な剣を持っているのかは、わからない。
しかし臓硯という蟲の魔術師を殺すのにこれほどの適役もあるまい。
遠坂は目の前の怨敵に一歩一歩近づいていく。
復讐に費やした十年間を、少しずつ踏みしめるように。
そうして臓硯の前に立つ遠坂。
周りに脅威は何もない。
そうして十年分の思いを込めて、蟲殺しの聖剣を振り下ろす。
「あなたの人生も今日で終わりよ。
500年、働いてきた悪事の重さを背負って……死になさい」
剣は振り下ろされ、地下室は浄化の光に包まれた。
5世紀もの間生き続けた大魔術師の最後である。
果たして遠坂は今、どんな気持ちだろうか?
復讐を果たして満足なのか?
それとも、復讐に費やした十年を悔いているのだろうか?
溢れる光に遮られ、遠坂の顔を伺い見ることはできない。
それでも、復讐という負の想念から解き放たれ、晴れ晴れとしていると信じたかった。
臓硯の体中の蟲を消しつくした聖剣は、その役目を終えたかのように崩れ落ち、残ったのは塵と消えた臓硯の服のカスだけだった。
そのままの姿で固まっている遠坂。
その後ろ姿に俺は何を見たのだろう?
「遠坂……」
遠坂はこちらを向いてくれない。
しかし、確かな声で返事をしてくれた。
「士郎も……勝ったんだ、あの魔獣に」
「ああ、危ないところだったけどな、遠坂も勝ったんだな」
遠坂はクルリとこちらを振り向き、満面の笑顔で俺に告げた。
「うん、わたしたちの完全勝利ね。ありがとう、士郎。貴方がいてくれて……良かった」
その表情に暗さはなく、これからの遠坂の人生の明るさを物語っていた。
「じゃあ外に出ましょ。これ以上、蟲くさいこの屋敷にいたら、臭いが移っちゃうわ」
遠坂と肩を並べ、必ず生きて帰るという約束どおり、俺たちは間桐の屋敷を後にした。