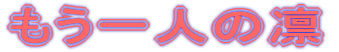 2章
2章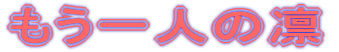 2章
2章
朝の光とスズメの鳴き声に目を覚ますと、そこは見覚えのあるリビングだった。
「……そうか、この世界に来て、遠坂の家に泊まったんだっけ」
すぐに理解できた。
ここは慣れ親しんだ我が家ではなく、そして俺の存在する世界ですらない。
たった一晩で納得できるなんて……どうやら俺は順応性に優れているのかもしれないな。
さて、時刻は朝の7時。今日はこれから何をすべきか。
とりあえず遠坂は学校に行くんだろう。
ならばそろそろ用意をする時間ではなかろうか。
とはいえ勝手に部屋に入るわけにもいかない。
そうだな、せめて朝食の用意だけでもしておいてやろう。
パカリと冷蔵庫を開ける。
なんと! 玉子しかないじゃないかっ。
これでは俺の料理の腕も発揮しようがない……
まあ、文句ばかり言っていてもしょうがない。
とりあえずパンはあるので、シンプルに目玉焼きとトーストにしよう。
寝起きの悪い遠坂の為にミルクを用意して準備完了だ。
キッチンのテーブルに二人分の朝食が見事に並ぶ。
「あれ〜、は〜や〜い〜の〜ね」
そこに現れる幽鬼少女リン。
いくら慣れているとはいえ、その目つきは尋常じゃない。
「ああ、簡単だけど朝飯作ってみたんだ。ほら遠坂」
そう言って手渡したのは冷たい牛乳だった。
「ん、ありがと」
腰に手をつけて牛乳飲みますポーズで一気飲み……う、美しくない。
「ふぅ。目が覚めたー。ありがとう士郎」
「どういたしまして、慣れてるからな」
「そ、そう。そうなんだ?」
「まあな、それより飯作ったって言っただろ、早く食べないと学校に遅刻するんじゃないのか?」
遠坂は自分の席に着き、トーストをかじる。
「あー、学校は今日から自主休講よ。
昨日のヤツラが現れたんだから、もう学校なんて行ってられないわ」
「ん? そうか、確かにあんなヤツラに襲われたんじゃ学校なんかに行ってられないな。
それなら今日は何をするんだ? っていうか俺は何をすればいいんだ?」
「別に。士郎は何をしていてもいいわ。寝ててもいいし、わたしの稽古に付き合ってもいいわよ。
わたしは午前中は剣の稽古、午後は魔術の鍛錬をするつもりだから」
「ふーん、それなら遠坂の稽古を見させてもらおうかな、別にやる事もないし」
簡単な朝食はそれで終わった。
「じゃあ庭に行こっか」
俺は元気に庭に向かう、遠坂の後ろ姿を追った。
稽古が始まって早一時間。
遠坂は竹刀を持ってイメージの敵と戦い続けている。
ボクシングでいうところのシャドーボクシングってヤツだ。
それをジーーーっと見続ける俺。
研ぎ澄まされた気合とともに放たれる剣は鋭く、力強い。
しかし同時に弱点も俺には分かってしまった。
このまま続けていても遠坂はこれ以上強くはなれない。
分かってしまったからには教えてあげなくてはならないだろう。
「遠坂」
遠坂は振るっていた剣を止め、こちらに振り向く。
「なによ?集中してるんだからあまり声をかけないでくれる?」
「分かってるんだろ? これはあまり理にかなった訓練とは言えないぞ」
「っ!!
な、なんでそんな事が分かるのよっ?」
「そうだな、まずはシャドーの相手のレベルが低い。
自分より格下とばかり戦っていると、いざという時に力を発揮できない」
「う」
「次に剣の稽古は、魔術と違って一人では出来ない。
相手がいなければ、それ以上の上達はないだろう」
「そ、そう。
士郎、アナタ随分と剣に自信があるみたいね……
それじゃあわたしと一勝負、いかがかしら?」
「そう……だな。俺はまだまだ未熟者だ。
でも、遠坂に教えてやる事は出来ると思う」
「そう、じゃあそこに置いてあるもう一本の竹刀を使って」
「いや、俺はこれでいい。竹刀だと遠坂に当たると危ないだろ」
俺は手に持つ雑誌をクルクルと丸めて棒状にした。
「ちょ、ちょっとアンタ舐めてるのっ?」
「別に舐めてなんかない。俺に打ち込む隙があったら遠慮なく打ち込んでいい」
そう、舐めてなんかない。
遠坂の放つ剣は鋭かった。
きっと彼女は何年もの間、剣の稽古を欠かしたことはないのだろう。
俺が剣の稽古を始めたのはたった数ヶ月前だ、努力の量は比べるのもおこがましい。
でも俺には最高の師匠がいた。
そして目蓋の奥底に焼きついている赤い外套。
遠坂はまだ知らない。
師匠と弟子。剣の技術というモノは、決して一人では成る事ができないということを。
俺は遠坂と向き合って構える。
その間合いは5メートル弱、いつでも打ち合いが始められる距離だ。
もちろん先手を取ったのは遠坂。
やる気に満ち溢れた剣を、その気合のまま俺にぶつけてくる。
「はっ!」
正眼の構えから俺に向かって切りかかってくる。
その太刀筋は鋭く、速い。
だが読みやすかった。
実戦経験のない遠坂の剣は、真正直に俺の急所を狙ってくる。
遠坂の目線、筋肉の動き、呼吸、そして気配。
それら全てが、彼女の次の狙いはここだと告げていた。
俺は、右に左に柳のようにかわし続ける。
手に持つ獲物は紙の棒、当然受ける事は出来ない。
しかし、そんなハンデすらも関係ないほどに、俺たちの力の差は開いていた。
それでも遠坂の目は必死。
俺に何度かわされようとも、その度に体勢を立て直し、決して諦める事はない。
「ハァハァ、ぐっ!」
苦しい呼吸も構わず、休むことなく俺に立ち向かってくる。
その必死な姿は、見ていて気持ちが良いものだった。
―――セイバーも俺と稽古をしている時はこんな気持ちだったのかな
ここにはいない俺の師匠を頭に思い浮かべる。
そして、セイバーならこんな時どうするのかな、とあの時の稽古を反芻していた。
次の瞬間、俺は目の前の少女の隙を選び、手に持つ棒を振り下ろす。
パッカーン
乾いた音が響き渡り、遠坂は頭を抱えてうずくまる。
「いったーーーーい」
顔を上げた遠坂は少しだけ涙目だ。
いくら紙の棒とはいえ、手加減無しに叩き込まれればそれなりの衝撃がある。
「ここまでだ、今ので分かっただろう?
遠坂の剣は鋭くて強い、でも実戦では通用しない」
遠坂は涙目のままスリスリと頭を撫でて立ち上がった。
「な、なんか、アンタに言われるとムカつくわね。
ハァ…でも事実だから受け止めるしかないか……わたしの十年間がこの程度だったなんてちょっとショックだけどね」
遠坂は心底がっかりしたようにため息をつく。
「十年間? そんなに一人稽古を続けてきたのか?
……それなら俺たちの間に力の差なんてきっとない。
ただ俺には最高の師匠がいた、それだけの違いだ」
「師匠か……
ふんっだ、わたしにだって最高の師匠がいたのよ。
十年前に昨日の影のマスターに殺されちゃったんだけど」
「殺された?あの影のマスターにか?」
「そ、十年前のあの日、わたしは全てを失った―――
父も母もそして剣の師匠も、全部」
「…………」
「すッごく強くて……とっても優しい人だったわ。
ふーんだ、アンタよりもずっとずーっと、強かったんだから」
「む、俺より強かったのか?」
「当たり前よー。アンタなんかの数倍強かったわ。
―――でも……それでも、あの魔術師には敵わなかった」
「遠坂、その魔術師って誰なんだ?」
遠坂は敵を見るような瞳でその一声を搾り出した。
「―――間桐臓硯。
十年前、父さんが命と引き換えに封印した悪魔。
そして昨日が封印から十年目、どうやら復活しちゃったみたいね」
俺はその名に聞き覚えがあった。
それは言峰の最後の助言―――大聖杯を狙っている間桐の大魔術士。
まさかこちらの世界でも悪事を働いているとは……
「あれから十年間、一日も休まず稽古してきたのに全部無駄だったなんて、さすがに落ち込むわね……」
「遠坂……」
「みんなの敵を討つんだって、死ぬ思いでがんばって来たのにな、えへへ」
ぺろっと舌を出して笑顔を作る遠坂。
それが本心からの笑顔じゃない事ぐらい分かってる。
俺には遠坂の心情が痛いほど分かってしまった。
理不尽な力によって全てを失った自分と、遠坂の姿が重なり合う。
それに今の話を聞いてしまったからには、俺はこの世界でやらなければならない事ができてしまった。
「無駄じゃない―――
十年間ずっとがんばってきたんだろう?
だったら、遠坂のその思いは決して無駄なんかじゃないんだから」
「え……?」
「遠坂の剣は鋭く、強い。
足りないのは一つだけ、経験だ。
戦いの経験さえ積めば、元々の下地はあるんだからもっともっと強くなる」
「…………」
「だから、俺が相手になる。
いつまでこの世界にいられるかはわからないけど、それまでお前の力になりたいんだ」
「し、士郎……」
「そんな顔するなよな。
元より遠坂には世話になってるんだ。その位させてくれたっていいだろう?」
「う、うん。ありがとう……」
「ああ、なら休憩は終わりだ。
この傷が癒えるまでには俺を超えてくれよな」
バンバンとちょっと強めに左腕を叩く。
俺の左腕は昨日のケガで無理に動かすことはできない状態だ。
「うん、うん! お願いします!」
俺は地面においてある竹刀を掴んだ。
真剣な稽古となれば、紙の棒では遠坂に失礼だ。
俺は彼女の欠点を指摘し、長所を伸ばし、そして俺を超える剣士に育てなければならない。
もちろん一切の手加減など出来はしないだろう。
例え短い間だろうと、俺たちは頼り頼られる師と弟子になったのだから。
「行きます!」
「ああ、思い切り来い」
竹刀を弾きあう音とともに、俺と遠坂の奇妙な共同生活がたった今、始まったのだ。
「いったーーーーーい! もっと優しく塗ってよね!」
リビングで奇声を上げる弟子が一人……
その顔は赤く腫れ上がり、せっかくの美人が台無しだった。
「士郎ったら全然手加減してくれないんだもん、レディーの顔に傷でも残ったらどうするのよー」
「一応遠慮はしたんだぞ、でも手加減したら意味ないだろ。
大丈夫、腫れてるだけで傷にはならないよ」
治療を終えた俺は最後にピシャと遠坂の頬を叩く。
「あー、痛かった。アンタもうちょっと薬の塗り方を勉強した方がいいわよ。
わたしじゃなかったら耐えられないところよ」
目じりに涙を溜めて、心底痛そうに文句を言う。
「わかった、わかった。明日からはもう少し上手く塗るからさ。
それよりも、そろそろ昼飯の時間じゃないのか?」
「あら?そうね、そろそろお昼にしましょうか。
……って冷蔵庫の中身、何にも無いじゃないのよー」
「そうだな、朝見た時もガラガラだったし」
慌てぬ俺とは裏腹に、遠坂は少し後悔しているようだった。
「はぁー、こんな事なら昨日のうちに買っておけばよかったわ。
家から出たら狙われるわよね、間違いなく」
「なんだ、それなら俺も一緒に行くよ」
「え?」
「大丈夫だって。いざとなったらこの家に逃げ込めばいいんだろ?
だったら二人いれば多分何とかなる、それにいつまでも家から出ないわけにも行かないだろう」
「そ、それもそうね。じゃあ悪いけど付き合ってくれる?」
「遠慮するなよ。世話になってるって言ったじゃないか」
「ふんっ、そういえばそうだったわね。食事代くらいはしっかり働いてもらわないと、わたしが困るんだからっ」
怒ったり遠慮したり相変わらず忙しいやつだ。
目の前のころころ変わる遠坂の表情に、俺も自然と饒舌になる。
「さっ、行こうぜ。朝飯少なかったから、もう腹ペコなんだよ」
「あ、ちょっと待ちなさいっ。
アンタねー、居候のクセに少しは遠慮しなさいよっ」
「早くしろよー、置いてくぞ」
後ろからダッシュで俺に追いついた遠坂は、そのままの勢いで俺の腕に抱きついてきた。
ちょっとだけ赤い顔で腕を絡めるその顔は、この世界に来て始めて見た遠坂の素顔だった。
「ふーんだっ、別に士郎の事なんてなんとも思ってないんだから。
でも、パートナーでいる間だけはちょっとだけ気を許してあげる、だからアンタもわたしの事を少しは信用しなさいよね」
そんな遠坂の姿を見て、なんだか子供みたいだ、と思うのは失礼だろうか。
「ああ、俺たちはパートナーだ。だからお前の事……信頼してる」
「うん、よしっ」
「ああ、行こうか」
商店街を腕を組んで歩く俺たちは、きっと恋人のように見えるだろう。
俺は、こっちの遠坂との距離が、ちょっとだけ近くなった事を幸せに感じるのだった。
無事買い物を終え、遠坂はキッチンで料理に励んでいる。
今日から俺たちは一緒に暮らすわけだが、それに伴って料理を当番制で作る事にした。
今日の昼は遠坂、夜は俺、そんな感じで順番に作っていく。
調理場にはエプロンをつけてフライパンと戦っている遠坂がいた。
俺のリクエストで今日の昼食は洋食になる予定だ。
さてさて、こっちの遠坂の料理の腕はどうかな?
かくして、目の前に並べられた洋風の食事を美味しそうに頂く二人。
むむむ、確かに美味い……だがっ。
俺は小さくガッツポーズをとる。
「ん? なによ、士郎? ガッツポーズなんかして」
「いやいやいや、なんでもない。今日の夕食を楽しみにしていてくれ」
「……?」
いつぞやの仕返しをこっちの遠坂にするのは気が引けるが、そもそも料理で負けるのは俺のプライドが許さないのだ。
決め台詞は「常に切り札は隠しておく、でしたー」で行こ♪
夕食が楽しみだ……
さて昼食が終われば、今度は魔術の鍛錬が待っていた。
当初の予定通り、遠坂は工房に篭り、基礎魔術の復習を行うみたいだ。
「あら士郎。剣術の方は見事だったけど、魔術の方も相当なのよね〜?
あれだけの投影魔術を扱えるんだし、期待しちゃうわ〜」
「むむむ、何かその言い方ムカつく。
―――いいだろう、八年間、鍛え続けた俺の魔術を見せてくれるわっ」
「全然ダメね、アンタ魔術の才能無いわ。八年間もなにやってたの?」
「くっ、強化と投影は成功してるじゃないかっ」
「強化と投影しか使えない中途半端な魔術師なんて聞いた事ないわ、ヘッポコ」
「くっ……屈辱……!」
「ふふっ、しょうがないからわたしが師匠になってあげる。こっちの世界にいる間だけだけど、多少はましになるでしょう?」
「ほ、本当か? それならぜひっ!」
「あら、さっきの剣の稽古の事、覚えてる? わたし、アナタになんて言って頼んだっけ〜?
わたし、礼儀には厳しいのよね〜、自分にも他人にも」
「くっ、……屈辱……!
―――よろしくお願いします、遠坂師匠……」
「うん、よろしいっ。
じゃあ今日から午前は剣で、午後は魔術の稽古ね。お互いがんばっていきましょう」
「ああ、午前はガシガシいくぞ」
「あら、午後はビシビシいくわよ」
バチバチと火花を散らす弟子と師匠。
俺たちは午前と午後で敬語を使い分けねばならなくなったのだ。
「フフフフ」
「ホホホホ」
二人揃って乾いた笑い声を上げる。
何か俺たちって歪んでる……かも?
こうして始まった遠坂と俺の奇妙な共同生活。
魔術の鍛錬でビシビシ鍛えられ弱音を吐く俺。
夕食時には俺の切り札料理に歯軋りする遠坂。
就寝前にはお茶を飲みつつまったりとする二人。
こちらの世界の遠坂は、ちょっとだけ子供っぽかった。
そりゃ並行世界と言っても、全てが全て同じと言うわけもない。
生活環境や周りの状況によっては、性格が変わる事もあるだろう。
しかし、それでも遠坂は遠坂だった。
剣の稽古に必死で取り組む遠坂。
魔術の拙い俺にため息をつく遠坂。
俺の作った料理に歯軋りをする遠坂。
そして、俺の事を信頼してくれる遠坂。
俺はこちらの世界でこのまま暮らすのもいいかな、と思い始めていた。
それほど目の前の遠坂との生活は楽しかった。
もちろん元の世界の遠坂よりも魅力的だというわけじゃない。
ただ、なんとなく、俺はこの世界に必要とされて召喚されたんじゃないのか、と思い始めていたのだ。
「はっ!」
目の前には竹刀を振るう遠坂。
その剣は相変わらず鋭く、速い。
あれから一週間続いた剣の鍛錬は、遠坂の剣の力を飛躍的に増大させていた。
くっ!
その鋭い剣に俺の予測も追いつかない。
ただ必死にその剣を弾き返すだけ。
しかし、声は出さない、表情にも苦戦の色は出さない。
遠坂の剣の師匠として、まだまだ余裕があると思わせておきたいのだ。
そうさ、男の意地ってヤツだ、ふんだ、悪いか?
そんな事を考えている間にも、遠坂の剣は次々と俺の急所に迫る。
―――くっ、コイツ、急所ばかり狙いやがってぇ、くそぅ。
そうして俺は表面上はゆとりを持って、遠坂の剣を捌き続ける。
結局、何合打ち合ったかは分からない。
ただ、今回も何とか師匠の面目を保つ事が出来たようだ。
冷や汗ながらに自ら隙を作り遠坂を誘ってみる。
剣をかわされ続けた遠坂は、一も二もなくその隙に喰らいついた。
その予想通りの剣戟を大きく弾き返し、唯一といっていい隙に全霊を込める。
「きゃ」
スパーンと、俺の竹刀が綺麗に面に入った。
「いったーーーーい!」
遠坂は頭を抱えてうずくまっている。
しかし、初日は俺のやり放題だった剣の稽古も、今日の遠坂の敗北はこの一回だけなのである。
「うぅ、ちょっと士郎、いくらなんでも思いっきり叩きすぎよー」
「遠坂、稽古中は敬語」
「くっ、いくらなんでも思いっきり叩きすぎだと思います……」
「すまなかった。あまりに遠坂の動きが良かったんで、手加減する余裕がなかったんだ」
「ほ、本当ですか!?」
「本当だ。初日とは大違いだ。
もう俺の教える事は殆どないのかも知れない。
これなら…………っ!」
「これなら……?なんですか?」
「い、いや何でもない。それよりそろそろお昼にしないか?」
「やったー、それなら敬語終わりっ。士郎、今日の昼食はアナタの番よー。
これだけ稽古をしたんだから、とびっきりの料理を作ってくれないと許さないんだから」
目の前の遠坂は飛び上がって喜んでいる。
どうやらこっちの遠坂は料理では俺に勝てないと認めたらしい。
その証拠に当番制と決めた料理も、徐々に俺が作る回数が増えていた、今のように。
まあ、それもいいかな、と思う。
俺の料理だけでこんなに喜んでくれるなら、作り甲斐もあるってもんだ。
かくして俺の作った昼食は今日も大盛況でした。
たった一人のお嬢様だけだけど。
つつがなく魔術の鍛錬を追え、俺たちは夕食を食べ終わっていた。
今日の夕食も作ったのは俺。
もう当番なんて有って無いようなものだった。
その代わりに、遠坂は夕食の片付けをしてくれている。
俺は、キッチンで洗い物をしている遠坂の背中を見ながら、食後のお茶を用意していた。
「あれ? 遠坂ー、紅茶切れてるぞ。替えの紅茶はどこにあるんだ?」
「あら、ホント? ごめんね、替えの紅茶も切れてるの。
今日はお茶にしま……っ!
ああ! わたしの部屋の棚にとっておきの一品があったわ。
せっかくだからそれ飲みましょう、士郎、悪いんだけど取ってきてくれる?」
「りょーかい」
俺は洗い物を続ける遠坂に返事をして、部屋に向かった。
遠坂の部屋に入るのは初めてではなかった。
もちろん、向こうの世界での話だが。
カチャリとドアを開け、初めて遠坂の部屋に入る。
その部屋は俺が知る遠坂の部屋と殆ど同じだった。
インテリアの配置とか、部屋の装飾とか、そういう形骸的なものじゃない。
部屋に篭る空気というか、雰囲気が同じだったのだ。
そして、俺は棚に置いてある缶を見つけた。
「これか……とっておきだけあって高そうだな」
缶を手に掴み、そのまま立ち去ろうとする。
しかし、その棚に並べられている本に少しだけ違和感を感じて、足を止めてしまった。
「これ、なんだろ?」
何冊もの洋書が棚には並べられている。
それは元の世界の遠坂の部屋と同じ。魔術関連の西洋の書物だ。
しかし、その中に一冊だけ異彩を放つ、漢字交じりのタイトルを見つけた。
「こんな本、向こうの遠坂の部屋にはなかったな」
何気なく俺はその書を手に取る。
「平家物語」と書かれたその本は、その棚の中でも異様な雰囲気を漂わせていた。
元来、書物には魔力が篭りやすい。
それが魔術書ならなおさらだ、何百年も魔力を溜め続けた書物はそれだけで一級の魔術遺蹟となる。
この本にも魔力を感じた。
それは僅かな魔力だったかもしれない、しかし俺は魅せられた様に、その本を開いてしまった。
パラパラと本をめくる。
漢字ばかりの難しい書だった。
そしてあるページで折り目がつけられている事に気づく。
「ココ……遠坂がよく読んだのかな?」
そのページには見た事もない魔獣と、それに立ち向かう武士の姿が挿絵として載っていた。
「平安時代……? この時代にも魔獣がいたのか……」
いつの間にか俺は、そのページの原文解説を読み始めていた。
源頼政という武士が、弓を使って魔獣を射殺す、そんな物語だった。
再び挿絵に目を戻す。
その絵の武士が持つ弓が、目に付いた。
もちろんただの絵だから解析はできない。
それでもその絵に込められた作者の思いが伝わってくるような気がした。
「ちょっと、士郎。紅茶を取りにいくのに何分かかってるのよー」
ガチャリと少し乱暴に扉が開き、遠坂が怒り顔で部屋に入ってきた。
「あ、と、遠坂? す、済まないっ! こ、これは別に覗き見したわけじゃなくて、そのー」
俺は覗きの現場を押さえられたように慌ててしまった。
いや、別にやましい物を見ていたわけではなかったのだが、何となくそう思ってしまったのだ。
「あら、何を見てるの? 士郎」
「この本、魔術書に混じってココにあるのが変だな、って。ごめんな、勝手に読んで」
遠坂はその本を一目見て、少しだけ悲しそうな顔をした。
「そう……その本を読んだんだ。
でも、いいのよ、もうその本は関係ないから」
「…………?」
「臓硯が使役していた魔獣が載ってるの、その本。
父さんが死んじゃった後にね、カタキを討つんだって随分研究したの。
でも、その魔獣は父さんがきっちり止めを刺したから、もう生きてはいなかったんだ。
その魔獣を倒すのに魔力の殆どを使ったから、父さんは臓硯なんかに不覚を取ったのよ」
幼い頃を思い出したのか、懐かしむようにその本を受け取る。
それにしても遠坂の親父はすごい実力だったって聞いている。
その凄腕の魔術師が魔力の殆どを使うなんて、どれほどの魔獣か想像もつかない。
俺たち魔術師は、ギリシャや北欧の神話には詳しいのだが、日本の神話には疎いところがある。
だから遠坂は、こんな本を見つけてきて研究したんだ。
俺は改めて遠坂の臓硯への憎しみを感じた。
「ねえ、士郎。たまにはこの部屋でお茶しようか?」
「あ、ああ。別にいいけど、どうして?」
「別に〜。ただ何となくこの部屋で士郎と話をしたくなっただけ。
この部屋に家族以外の人が入ったのって、今日が初めてなんだ……」
「そうか……なら今日は寝るまでずっと、ここで話をしよう」
「うん、わたし、お茶の準備してくるね」
そう言って遠坂はキッチンへ向かっていった。
残された俺は手に持つ和書に一瞥をして、元の場所にそっと戻しておいた。
既に夜は更けて、二人のお茶会も終わりが近づいていた。
あれから二人、何でもないことを話し続けた。
曰く、柳洞寺の住職が気に入らないだの。
曰く、この間の友達が異常に虎が好きだの。
些細な日常の一コマを喜々として話す遠坂。
その姿は年相応で、きっと魔術なんて知らなければこの少女は幸せに過ごせたのだろう、と思わせた。
「士郎? なに黙り込んでるのよー?
あー、まさか、もう眠いなんて言わないでしょうね」
「ははっ、そうだな、そろそろ眠くなってきたかもな。
それにしてもどうしたんだ? 今日はやけにご機嫌だな?」
「ん? そうかしら?
―――うん、きっとその通りかもね」
そう言って笑う遠坂は幸せそうだった。
「ね、士郎。
腕の傷、もう治ってるんでしょう?」
「……ああ、気づいてたのか?」
「まあね、もうすぐ治る筈だし」
「そうか」
「そうよ、それじゃあこの共同生活も、今日で終わりね……」
遠坂は真面目な顔で、小声だがハッキリとそう言った。
「―――明日、戦いに行くのか?」
「うん、士郎は腕も治ったんだし、もう好きにしていいわ。
この家に残っても構わないし、元の世界に戻る方法を探しに出ていってもいい」
「…………」
そこまで言って、遠坂は少し俯いた。
そして迷いを吹っ切ったのか、ちょっとだけ今までよりも大きな声で話し始めた。
「ごめんね、士郎。本音を言うわ。
わたしは、あなたに一緒に戦って欲しい……
死ぬかもしれないわ、だから仇を討てたら士郎に全部あげる。
お金だって家だって……その、わたしの初めてだって…
だから、お願い…わたしと一緒に戦ってください……」
それは心底からの遠坂の願いだった。
わたしと一緒に行ったら死ぬかもしれない。
それでも共に戦って欲しい、と俺を信頼しての言葉だった。
ただ俺は少しだけムッとした。
そしてそんな俺を見て遠坂は悲しそうな顔をする。
NOと受け取ったのだろう、相変わらず勘違いの多いやつだ。
「わたしの体ってそんなに魅力……ないかな?」
プチンと来た。
「そんなわけあるか、バカ。
遠坂、お前は勘違いしている。
例えお前が俺の知る遠坂じゃなくても、お前の頼みを断るわけないだろう。
なんで俺を信じてくれないんだ! 俺たちはパートナーだろう?
ただひと言、一緒に戦って欲しい、と言えば喜んで俺はお前に力を貸す
―――だから、体を売るなんてそんなコト言っちゃだめだっ」
「…………!」
「遠坂、俺が怒ってるのがわかるか?」
「うん、ごめんなさい。
……わたしが悪かった…です、だから……私のこと、嫌いにならないで」
遠坂は目じりに涙を溜めてそれだけを言うのが精一杯だった。
親に怒られる子供のように、自らを嫌いにならないで欲しいと訴える。
その姿に俺は、心臓を鷲掴みされる程の切なさを覚えた。
次の瞬間、俺は遠坂をギュッと抱きしめていた。
同じように遠坂も俺の体をギュッと抱きしめている。
「士郎、もっとぎゅっとして……」
俺はもう少しだけ力を込めて、遠坂を抱きしめる。
「温かい…………士郎、大好き……」
小さな声だが、確かに俺に聞こえるように遠坂は「好き」と言った。
俺たちはこの世界では、確かに他人だった。
初めて会った時、遠坂は俺の事を知らなかった。
それでも今は心が通じ合っている。
目の前の遠坂が、俺の知る遠坂と別人かどうかなんて関係ない。
ただ愛しかった―――
目の前の少女が愛しかったのだ。
「士郎、キス……しない? ううん、キス……して…下さい」
この世界での遠坂との初めてのキスは、本当に綺麗で、清らかな口付けだった。
「えへ、ね、今日は一緒に寝ようよ。ほら、このベッドで。
いいでしょ?」
「ああ、でも寝るだけだぞ」
「うん、ありがとう―――士郎」
俺たちは二人抱き合って夜を迎えた。
もちろん体を重ねるような無粋な真似はしない。
ただ、お互いの体温を感じて、抱き合って寝ただけ……
お互いがそれぞれを大切に思い、それぞれを温かく思っている。
そんな温かな夜が、俺たち二人の最後の夜だった―――